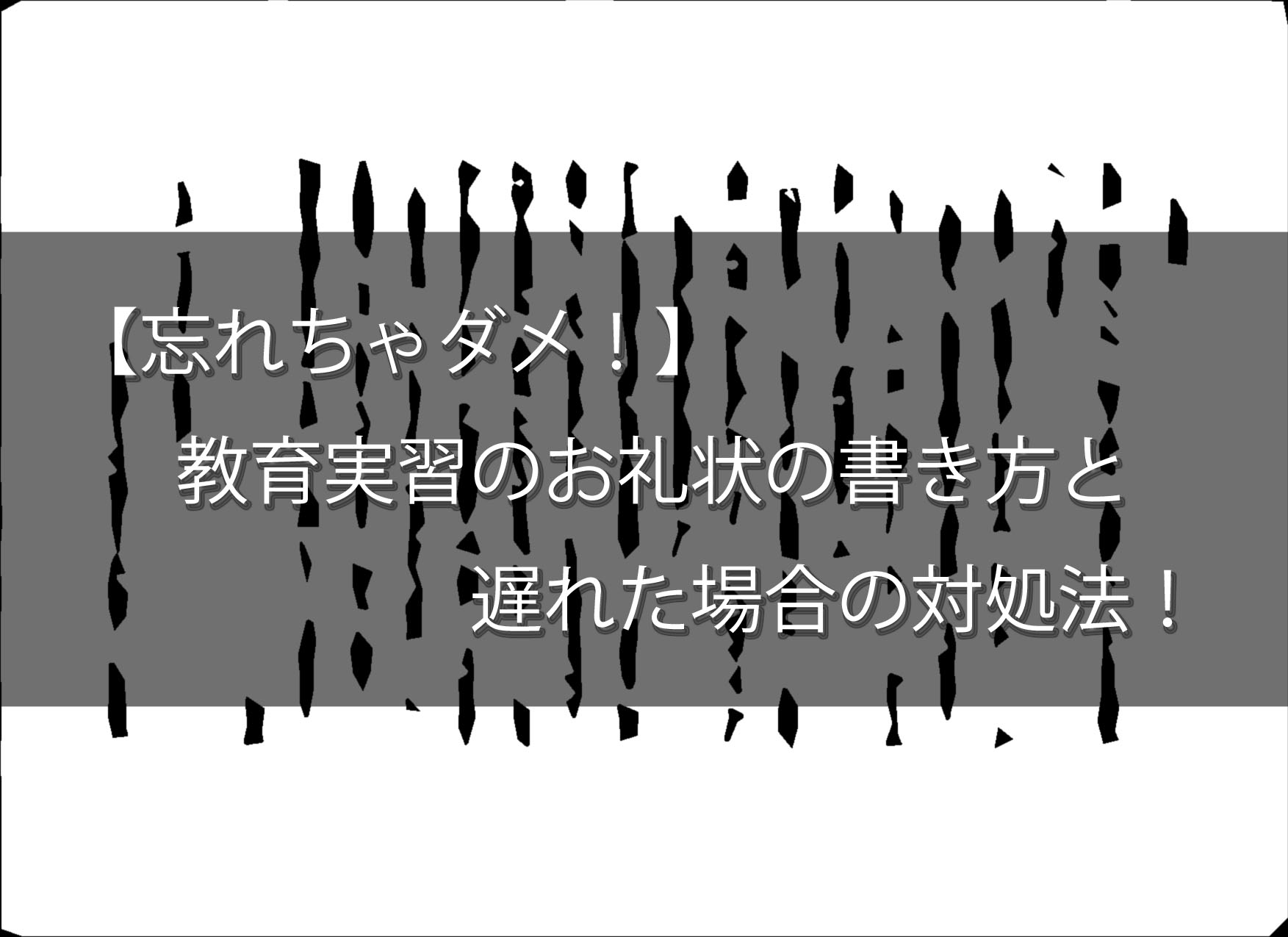【舌】身体の慣用句とその使い方・例文

Warning: Undefined array key "toc_min_h_count" in /home/gecko367/jiji-chatch.com/public_html/wp-content/themes/dp-colors/inc/scr/toc.php on line 11
Warning: Undefined array key "toc_position" in /home/gecko367/jiji-chatch.com/public_html/wp-content/themes/dp-colors/inc/scr/toc.php on line 19
Warning: Undefined array key "toc_main_title" in /home/gecko367/jiji-chatch.com/public_html/wp-content/themes/dp-colors/inc/scr/toc.php on line 48
今回は舌を使った慣用句ですね。字面だけ読んでいくと、どうやったらそれが出来るんだ!というものばかりで面白いですが、意外とまだ見たことのない慣用句もあって面白んじゃないかいと思います。
というわけで、早速見ていきましょう!
「舌」を使った慣用句
舌が肥える
「舌が肥える」は美味しいものをよく食べていて味の善し悪しがわかる、また美味しいものを好むという意味ですね。「口が肥える」とほぼ同じ意味なのでどちらを使うかはお好みで。
舌が回る
つっかえることがなくスラスラと台本を読むように話すこと、口が達者であるさまを「舌が回る」と表現できます。
舌がもつれる
上記とは逆に、うまく話ができずにつっかえてしまったり、思い通りに話せないさまを「舌がもつれる」といいます。アドリブでなんかやってと言われると大体舌がもつれる人が多いですが、中には用意してきたんじゃないの?というような一芸を披露する人もいてすごいですよね。
舌先三寸
「舌先三寸」は口先が達者なことを指す言葉ですが、口先だけが巧妙という意味合いなので「舌が回る」よりも下手くそな話術であるときに使うと良いかもしれません。
舌鼓を打つ(したつづみをうつ)
おいしいものを味わったときの満足感に舌を鳴らすことを「舌鼓をうつ」と言いますね。この意味で使われることがほとんどですが、昔の表現だと不快な気持ちを表すという意味もあったのだそうです。いまでも後者が使われていたとしたら、どちらの意味で舌鼓を打ったのかややこしくなりそうですね。
舌の根の乾かぬうち
「舌の根の乾かぬうち」は前言をすぐに撤回したり反対のことを言ったりする人に対して、非難の意味を込めて使われる言葉です。言い終えてすぐに、という意味がありますね。発言がコロコロと変わる人ほど信用出来ないものですので、よく考えて発言することが大切です。
舌を出す
ペロッと舌を出してごめんなさいとごまかす仕草、ありますよね。「舌を出す」は自分の失敗をごまかす時に使われる仕草としてよく使われます。あまり使われないですが、別の意味としては陰で馬鹿にする、心の中であざわらうといった意味も。
舌を鳴らす
これは舌を上顎にあてはじき、チッと鳴らす舌打ちというやつです。不満や軽蔑の気持ちで使われることが定着していますが、舌鼓を打つにみられるように感嘆するさまもあらわせる厄介な(?)表現です。もちろん状況によって意味が変わるので、上手く使い分けると良いでしょう。
大抵の場合、不快感を表す時は擬音をまぜたりしますが感嘆する時は「舌鼓を打つ」などの文字のみを使うことが多いように思います。美味しい料理を表現する時に「チッ」と書くと明らかにマズそうですからね…。
舌を巻く
相手に圧倒されてとても驚いたり関心することを「舌を巻く」といいます。「圧巻」などとも言い換えられますね。
筆舌に尽くしがたい
言葉では言い表せないくらいのことってありますよね。そういったときに使うと効果的なのがこの「筆舌に尽くしがたい」でしょう。なんだかわからんが、とにかくすごい!という状況で使えばいいので割と汎用性が高いです。
舌端火を吐く(ぜったんひをはく)
ものすごい勢いで論じてまくしたてるさまを「舌端火を吐く」と言います。まさに言葉で攻撃しているなといいたくなる時に使うといいですね。
舌の剣は命を絶つ(したのつるぎはいのちをたつ)
これは慣用句ではなくことわざですね。言動を慎まないせいで命を落とすたとえです。言うべきではないことを行ってしまうことは稀にあること。
それが命に関わるとは露にも思わないわけですが、昔は目上の人に対して失言しただけで打首とかあったでしょうから、そう考えると現在はゆるくなったほうだとは思います。でも経験上やっぱり不用意な発言をするものではないな、と思いますね。口は禍のもととも言いますし。
舌は禍いの根(したはわざわいのね)
「口は禍のもと」(口は禍の門)という故事成語がありますが、それと対になるのがこの「舌は禍いの根」でしょう。口が門であるのに対し、舌は根ということでどちらも禍に大きく関係しそうな表現ですね。昔から禍は言葉から起こるものだから、ということでこのように言われてきたのでしょう。
舌も引かぬ
「舌も引かぬ」とは、まだ言い終わらないうちにとか、言い終えてすぐ、という意味がある慣用句ですね。「舌の根も乾かぬうちに」と同じ意味となります。
舌を食う
これは舌を噛み切って死ぬという意味の慣用句。現在では使われることはほぼありませんね。舌を切ると死ぬという話はよく聞きますが、実際には舌癌切除のため舌を切断したりすることもあるため、切ったところで死ぬわけではないのです。
舌を吐く
これも現在はほぼ使われることのない慣用句ですが、ひどく呆れるという意味があります。呆れてものも言えない時に使ってみると良いかも。ただし、読んだ人がこの慣用句を知っているかが重要ですが。
舌を振るう
またまた使われない表現ですが、「舌を振るう」は非常に驚いたり、恐れるという意味があります。ですが舌を振る動作を実際にやってみると、全然怖いときにする動作とは思えませんね…むしろおちょくっているようにも思えるのですが…。
それとは別に、よどみなく強くしゃべる様子(雄弁)であることも「舌を振るう」で表現できます。今ではこちらの意味で使われることがほとんどでしょうね。
呂律が回らない(ろれつがまわらない)
酒によったりして言いたいことが言えず、舌足らずになって言葉がはっきりとしないときに使うのがこの「呂律がまわらない」ですね。当然ながら、お酒によっている時に使われることが多いですが、それ以外でも呂律が回らないことはあるので使い時はそれほど限定されるわけではありません。
まとめ
はい、というわけで今回は「舌」を使った慣用句をまとめました。後半は現在では使われないものもいくつかありました。舌を使うのは食べ物を味わう時や話をする時というのは昔から変わらないんだなぁ…というのがこれらの慣用句から感じられます。
個人的に気になったのはこれ。「舌は禍の根」です。自分の周りで禍が起きないよう、自分の発言に少し注意して周りの人を傷つけていないかを自分なりに反省してみてもらえればなと思います。