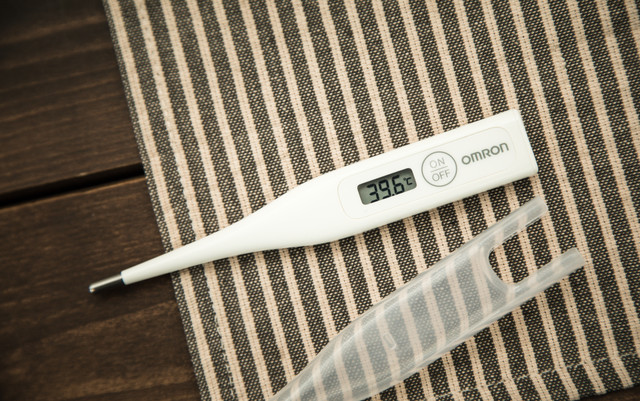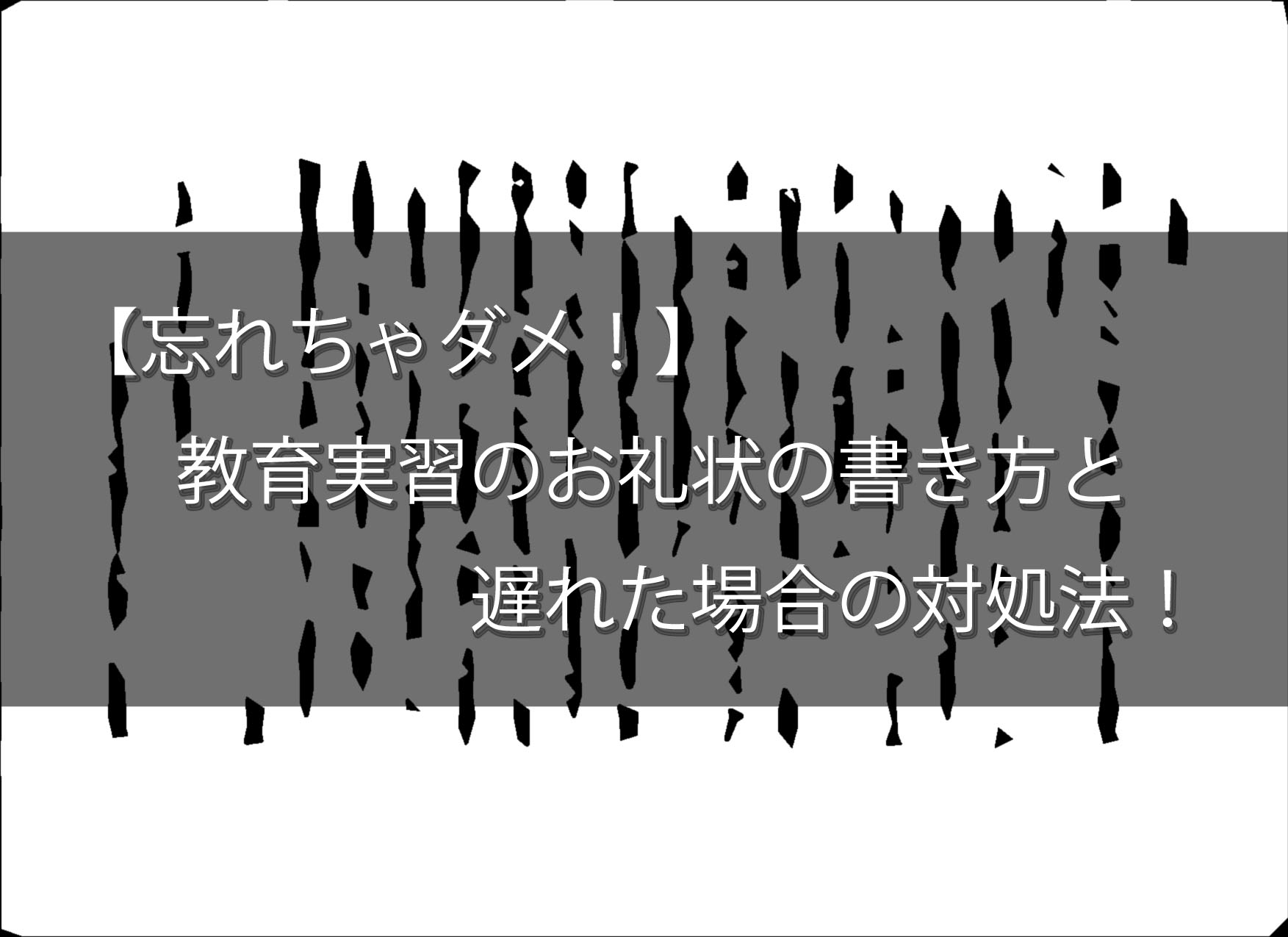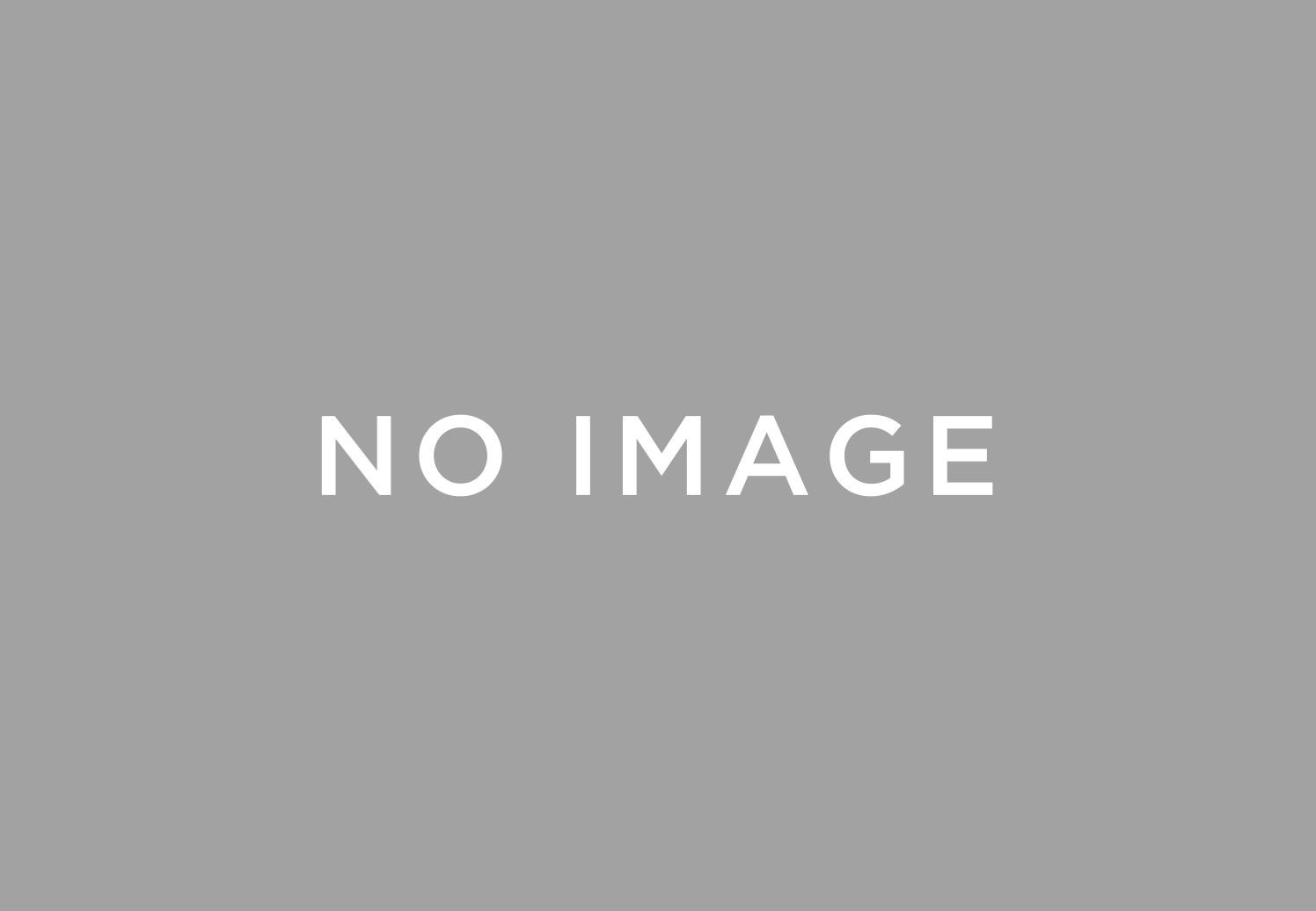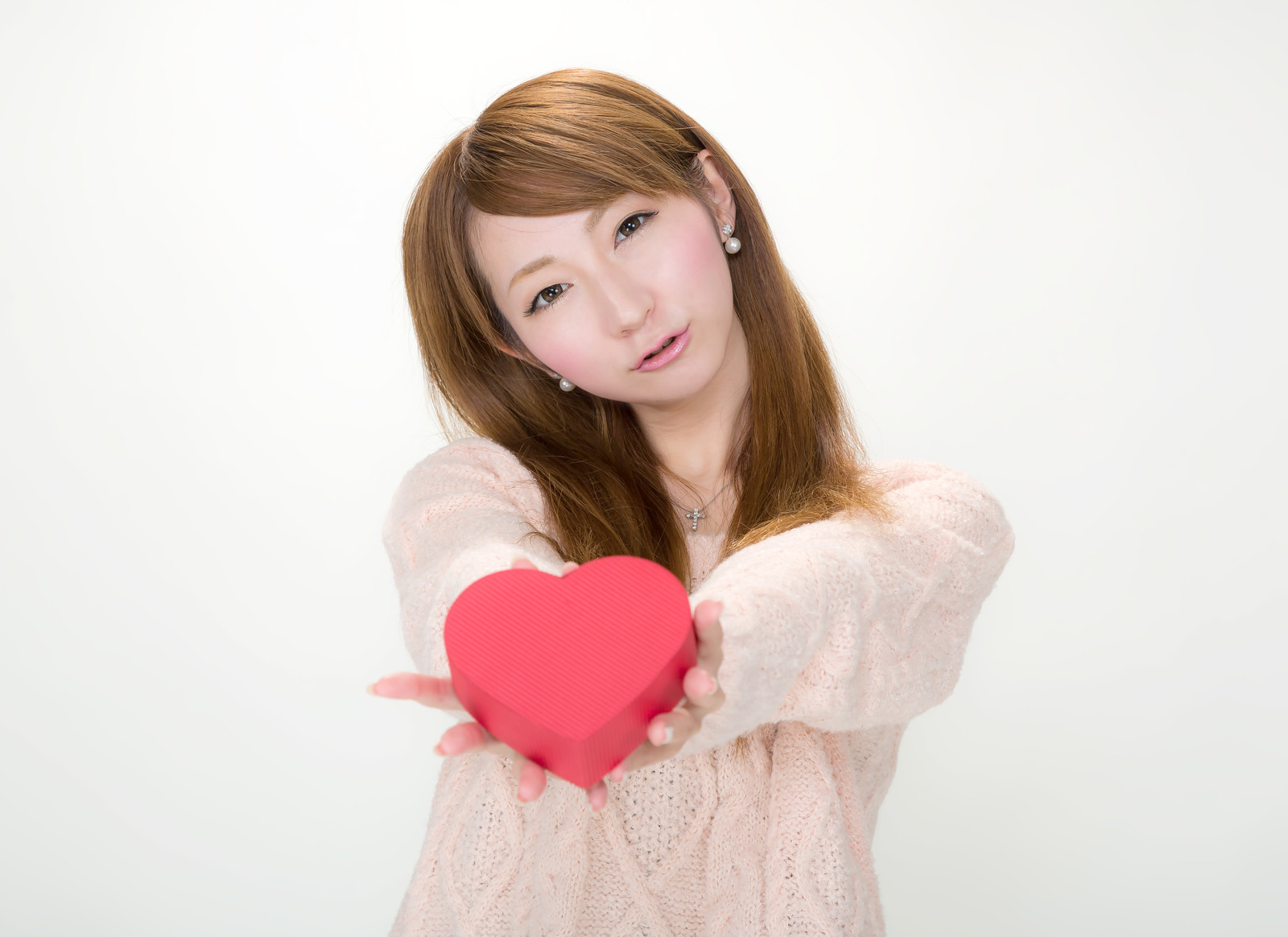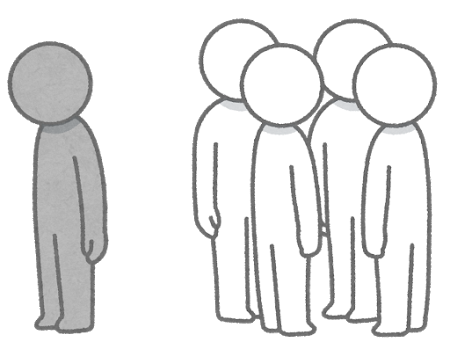2月って何日までだっけ?なんで月によって日にちにばらつきがあるの?という疑問を解消します

Warning: Undefined array key "toc_min_h_count" in /home/gecko367/jiji-chatch.com/public_html/wp-content/themes/dp-colors/inc/scr/toc.php on line 11
Warning: Undefined array key "toc_position" in /home/gecko367/jiji-chatch.com/public_html/wp-content/themes/dp-colors/inc/scr/toc.php on line 19
Warning: Undefined array key "toc_main_title" in /home/gecko367/jiji-chatch.com/public_html/wp-content/themes/dp-colors/inc/scr/toc.php on line 48
2月は年によって28日だったり、29日だったりとばらつきがありますよね?
なぜ2月にはこのようなばらつきがあるのでしょう。
今回は2月のばらついた日にちについてお伝えしますね。
月によって日数がばらついているのはなぜ?
2月のうるう年も謎ですが、奇数月と偶数月で日にちがばらついています。
基本的には偶数月が30日、奇数月は31日です。
これはかなーり昔にユリウスという政治家が、「1年は365日にする!」と明言しました。
紀元前の話で1月1日からユリウス暦と名づけて現代まで続いています。
そんな昔の話なのに、現代まで繋がって使われ続けているのは不思議な感じがしますね。
よくここまで世界に広がったものです。
1年を365日にしたのはいいものの、12で割ってもあまりがでてしまうんです。
なので、奇数月・偶数月で日付を割り振ることにしました。
割ってもまだあまる日にち
上記のように数字を割り振っても366日になってしまうんです。
昔は1年の終わりを2月にし、3月から新年ということにしていました。
1月が新年じゃないのは不思議な感じがしますね。
なので、もう年も終わるんだから2月日にち削ってもいいよね?といった形で1日削られてしまったのです。
2月を終わりにするのはやめよう!
1日削られてしまった2月ですが、やはり新年が3月からというのが具合よくなかったんでしょうね。
ユリウスは1月を初めで12月を終わりにすると決めました。
しかし、2月の1日は削られたままです。
4年に一度のうるう年もそのまま残して現在の状態にしたんです。
皇帝のわがままで日数が変わった!
先ほど偶数月が30日で奇数月が31日に割り振られたと説明しました。
しかし気が付くことありませんか?
偶数月なのに8月が31日まであるんです。
なぜ8月が31日までになったかというと、アウグストゥスという人が皇帝になった際、「なぜ自分の生まれた月が30日しかないのだ!」とダダをこねて激怒したんです。
それだけで激怒する皇帝も器が小さい気がしますが、そのせいで8月は31日までとなったのですよ。
皇帝というくらいですから権力が相当あったんでしょうね。
だからこそ、日付変更を可能にしたのです。
つじつまを合わせるために8月以降の月は偶数月が31、奇数月が30日になっています。
え、また366日になってる?!
つじつまを合わせたはずなのに、2月が終わりの月じゃなくなって、またも日にちは366日になってしまいました。
どうしたかというと、元々少なくした2月からまた1日引いたのです。
上記の話だけだと、2月は29日あるんですが、さらに1日削ってしまったのです。
2月をここまで日にちを削ったのはアウグストゥス!
自分の生まれた月が30日しかないとプリプリ起こってしまいにゃ2月はもう削れてんだからまた削っても問題ない!と削った神経がわかりません。
なんで月の均等化をしなかったんでしょう?
そこまで考えるのがめんどくさくなってしまったんでしょうね。
しかし、現代を生きているあかまるたちは、2月が29日ある方が不思議です。
2月が存在しなかった!?
実は、このユリウス歴が採用される前は1月2月に当たる月がなかったんです!
ロムルス暦という暦が使われていましたが、この暦でいくと3月から12月まで月は10日しかありませんでした。
農業をしない期間は暦の割り振りがなかったのです。
かなり変則的な暦なので現代人の感覚からすると「変」としか言いようありませんよね。
流石に使いにくい暦だったので、古代ローマ王が現在の形に近いものを作りました。
それが「ヌマ暦」というものです。
このヌマ歴では日付が29・31日しかありません。
当時偶数というのは割り切れるということで不吉だったそうです。
昔もうるう年はそんざいしていた!
昔の暦の日付は355日しかありませんでした。
現在とかなり違うので、月の周期もだいぶ変わるのが早かったそうです。
なので、うるう年をいれてどうにか調節していたそうですよ。
ただ、世界では戦争していたりして国と国の調節がきかず、各地方でバラつきが多かった模様。
場所によっては、季節と暦で2ヶ月以上も違いが出ていたほどです。
当時の人間たちはかなり大変だったでしょう。
暦を統一させるだけでも一大事だったんですね。
現代だとネットの普及により、どんなところにいてもネットに通信する媒体さえあれば情報がすぐ伝わります。
ちょっと昔では考えられないくらいネットは普及しました。
昭和時代だと携帯電話は高価で持てず、デートの約束はお互いの実家の電話番号だったのが嘘のようです。
誕生日がうるう年の人はどうしてる?
そう、うるう年が誕生日のひともいますよね。
昔の人は役所に届けるときに1日ずらして書いていたんだそう。
現在でもたまにテレビでそのまま出して書類上では20歳でもすでに40歳以上なんていうのもありますね。
そのときは2月28日の午後12時(もしくは3月1日)に年をとると考えたほうがいいでしょう。
まとめ:地球は微妙に24時間ではない
いかがでしたでしょうか?
地球は24時間周期で一回転していますが、厳密に言うと24時間ではないのです。
だから日付けも微妙に合わなくなってしまうんです。
それをなくすためにうるう年が設けられました。
この記事があなたにとって役に立つことを祈っています。