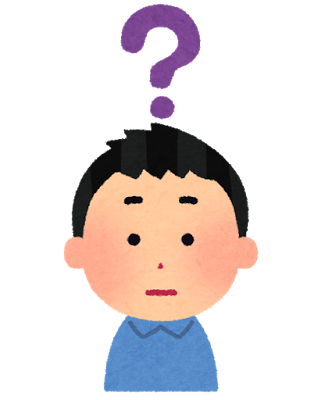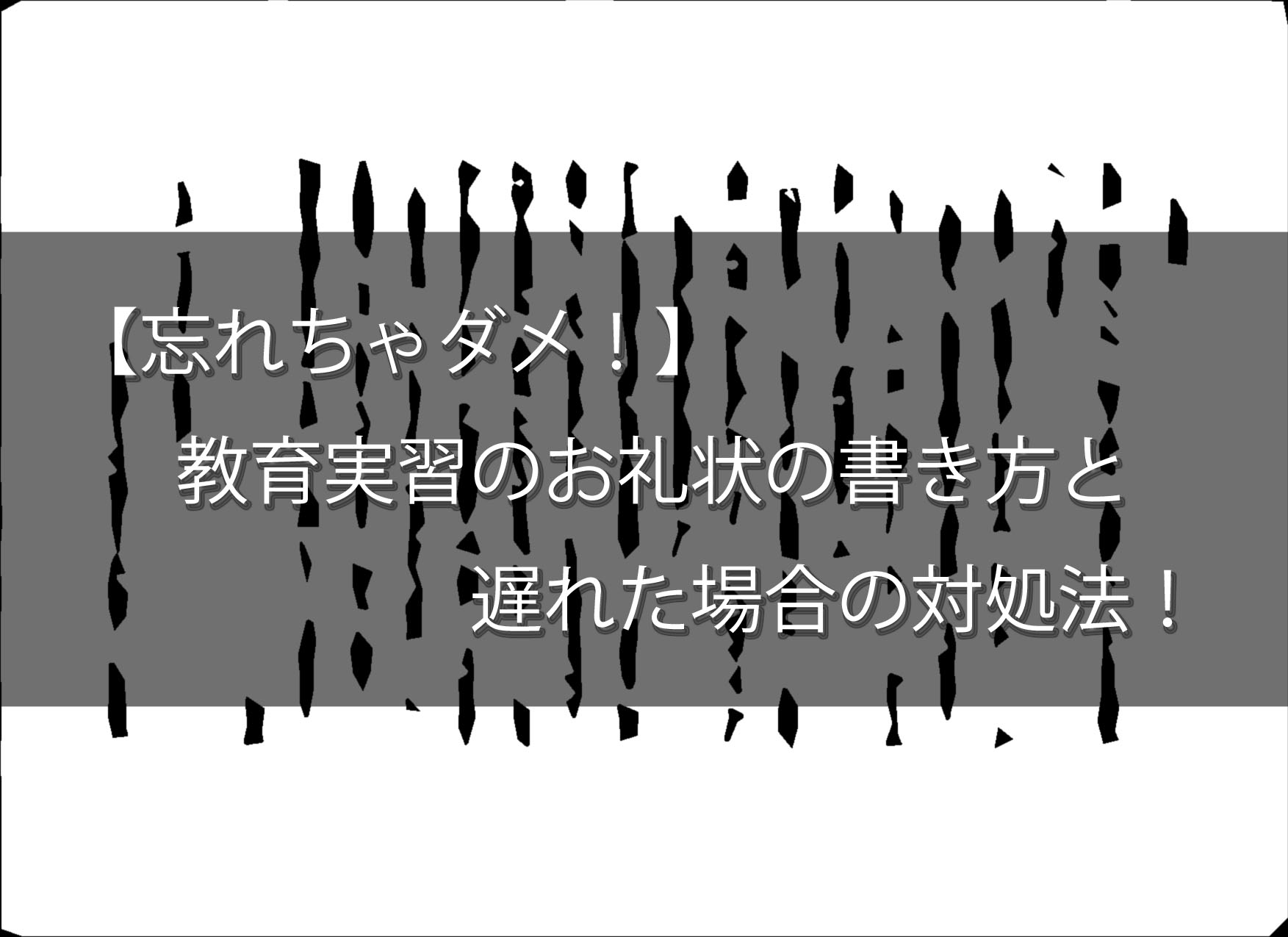【首】身体の慣用句とその使い方・例文パート1

Warning: Undefined array key "toc_min_h_count" in /home/gecko367/jiji-chatch.com/public_html/wp-content/themes/dp-colors/inc/scr/toc.php on line 11
Warning: Undefined array key "toc_position" in /home/gecko367/jiji-chatch.com/public_html/wp-content/themes/dp-colors/inc/scr/toc.php on line 19
Warning: Undefined array key "toc_main_title" in /home/gecko367/jiji-chatch.com/public_html/wp-content/themes/dp-colors/inc/scr/toc.php on line 48
はい、今回は首を使った慣用句ですね。実用的かつ頻繁に目にするものが多いのが特徴ですが、きちんと意味を理解して使えているでしょうか。ほとんどが一度は見たことがあるものだと思いますので、ぜひそのあたりもチェックしながら見てもらえればなと思います。
というわけで、早速見ていきましょう!
「首」を使った慣用句
首が飛ぶ
しょっぱなからひどい字面の慣用句ですが、「首が飛ぶ」は職を失う、免職・解雇されるといった意味になりますね。自分から仕事をやめるのではなく、会社側から辞めさせられるという状況で使うのが適切です。
意味合い的には「首になる」とほぼ一緒と思って差し支えないでしょう。
首が回らない
借金の返済などで生計が立ち行かないとか、やりくりができない状態のことを「首が回らない」と表現しますね。企業においては借入金は設備投資などに不可欠なのですが、個人で借金をすることは稀だと思います。
しかし現実を考えればクレジットカードの支払いやカードローンなども借金なんですよね。言葉巧みに借金というイメージを変えてお金を借りさせる手法って色々あるんだなと思うと少し怖いような気も。
首にする
「首にする」は会社などを解雇・免職するという意味ですね。首を切るとも。会社側が行うのが「首にする」で、「首が飛ぶ」「クビになる」のが労働者側です。どちらがされる側かを勘違いしないように気をつけましょう!
首を切る
こちらも会社側が使う言葉で、「首にする」と同じ意味となります。もう一つの意味は、打ち首にする、ですね。打ち首とは罪人の首を刀で切り落とす処罰のことで、いわゆる斬首刑になります。ちなみにこの方法は処刑人が下手くそだと1度で切り落とせず何度も刀を振り下ろすことになり、非常にむごたらしいものになるのだそうです。現在この処刑方法は日本では行われていません(世界でもサウジアラビアのみ)が、もしあると考えると怖いですね。
首を突っ込む
とある事柄に関心を持ち、深煎りしたり没頭することを意味するのが「首を突っ込む」ですね。しかし実際には「人の話に口を出す」などマイナスの意味で使われることが多いです。
首を長くする
ある事柄に期待して楽しみに待ちのぞむさまを「首を長くする」と言いますね。鶴のように首を長くする、というところから転じて「鶴首」でも同じ意味になります。。
実際に首が長くなったら怖いのですが、語源は待ち人を今か今かとあっちを向いたりこっちを向いたりして首を伸ばすさまからきたとか。長くなると言うほどではありませんが、多少は伸びたかもしれませんね。
首を捻る
説明されたことなどに対して、納得ができず考えることを「首を捻る」と表現しますね。概ね「考え込む」と同じ意味です。私もなぜこんなことに…と首を捻ることが最近多いです。
鬼の首を取ったよう
別に大したことでもないのに、とても大きな功績や手柄を立てたように思い喜ぶたとえを「鬼の首を取ったよう」といいますね。鬼は昔から怪物や神、あるいは冷酷な人のことを指す言葉ですが、実際には存在しないものです。(冷酷な人はいますけど)
ですので実際に鬼を倒せたらすごいことなんですけど、それはできない話なので間抜けだなぁ…となってしまうのですね。
小首をかしげる
人が話していることなどに対して、怪しいなとか不思議に感じたりした時に首を傾ける動作のことを「小首をかしげる」といいます。ちなみに小首とは、首のちょっとした動作のこと。
寝首を掻く
寝首を掻くは寝込みを襲って首を斬ることを言う言葉。そこから転じて、今では卑劣な手段で相手を陥れることという意味で使われるのがほとんどですね。
真綿で首を締める
「真綿で首を絞める」というとちょっと字面が怖いのですが、じわじわと苦しめて追い詰めることを言います。一気にドカーンと追い詰められると大ピンチなわけですが、まだ耐えられる…という具合にじわじわ追い詰められたらメンタルも疲弊してしまうのでタチが悪いですね。
雁首を揃える(がんくびをそろえる)
関係者が整列することを「雁首を揃える」と言いますが、低俗な言葉なのでビジネスシーンなどではまず使わない言葉です。どういう場合に使うかというと、例えば企業の組織的な犯罪などで経営者らがそろって出頭したときなどでしょうか。相手を憎たらしいと罵って言う言葉ですので、使い時は間違えないように!
鎌首をもたげる
鎌って曲げた背筋を戻して首を持ち上げる途中のような姿勢に見えますよね。「鎌首をもたげる」は良くないことが起こるきざしがあったり、怪しい活動が活発化するといった意味がある慣用句です。。
思案投げ首(しあんなげくび)
いい案が思い浮かばなくて困ってしまい、首をかしげる様を「思案投げの首」といいいます。考えることを止めているわけではありませんが、字面を見るともう色々諦めているようにも見えますよね。
首が危ない
「首が危ない」とは、解雇されそうだという意味で使われる言葉ですね。「首にする」とかと同じようにフランクに使える(?)慣用句。
まとめ
はい、というわけで首を使った慣用句パート1をまとめました。これも実用的かつ見かける頻度が非常に高い慣用句ばかりでしたね。「首にする」などのちょっとマイナスだったり怖い意味の言葉が多い、というくくりでみていくと覚えやすいかも。
まあ首というのは命に関わる部分なので、ある意味間違ってはいないですけども。というわけで、引き続きパート2もチェックしてみてくださいね!